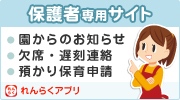2月の若竹通信
お餅つき
1月21日にお餅つきをしました。例年、お手伝いして頂く日本児童野外活動研究所(日野研)の方々によると、コロナ禍を餅つきを境に止めてしまった団体が多いとのことですが、若竹幼稚園では、大きな臼と杵が健在です。餅米も、園庭にしつらえた竈に薪をくべ、大きな羽釜の上にのせたせいろで蒸します。薪が燃えるときの独特のにおいが、餅つきの気分をいっそう盛り上げます。
園児さん達も3回ずつよいしょ、よいしょとお餅をつきました。今年はつぼみ組さんも先生に手伝ってもらいながら、つくことができました。楽しい思い出になってくれることと思います。
ご協力頂いた保護者の方、ありがとうございました。片付けまでお手伝い頂き、大変助かりました。また、近隣の方々には煙などでご迷惑をおかけいたしました。普段からの変わらぬご理解、ご協力に厚く御礼申し上げます。
山茶花と蝋梅
秋から冬にかけて、童謡「たき火」にも歌われている山茶花が園庭の東と西で咲き誇っています。大きな紅の花で、ついつい「咲き誇る」という表現を使いたくなります。
山茶花が盛りをほんの少しすぎ、花弁を1枚、2枚と落とし始める頃になると、園庭にある蝋梅のきれいな黄色い花が満開になります。2m程の高さの木で園庭の隅っこにありますから、あまり目立ちませんが、甘い、良い香りをいっぱいに放ち、春がそこまで来ていることを知らせてくれます。
お手紙ごっこ
年長さんはひらがなの練習の総仕上げの意味もあり、お手紙ごっこをしています。教室の中にはお手紙を出すための「ぽすくま」が書かれた大きな郵便ポストがあり、そこに投函されたお手紙は、教室の前に並んでいる、年長さん一人ずつのポストに届けられます。
練習して上手にかけるようになったひらがなで、はがきの書き方のルール通り、はがきの表にお友達の名前を書き、裏には「あしたあそぼうね」「すきなぽけもんはなんですか」… 話してしまえば、あっという間に済んでしまうようなことでも、大切な大切なお手紙になります。
節分
今年の節分は2月2日の日曜日なので、幼稚園では少し早めて1月30日に豆まきをしました。ホールを使い、各学年ごとに「鬼は外、福は内」のかけ声で、自分が作った鬼のお面に豆をぶつけます。
本当は、園児さん達の作った鬼のお面はかわいすぎて、とても「鬼は外」という気分になれません。むしろ「ほら、一緒に遊ぼ。夜になると座敷童も遊びに来るよ。」なんて声をかけたいくらいです。